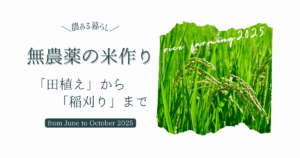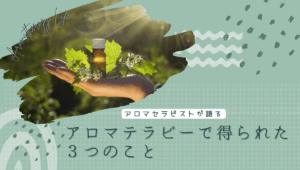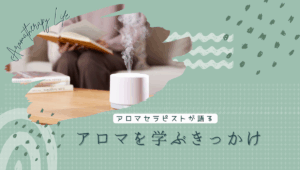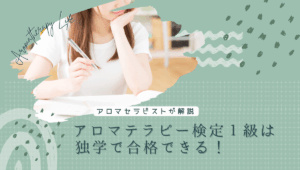アロマテラピーについては、過去にこんな記事を挙げたことがあります。


そこでは、ざっくり一言で表現すると、「精油(エッセンシャルオイルともいう)を用いた自然療法」であることをお伝えしました。
それゆえ、「精油」はアロマテラピーにとっては欠かせないものになるのです。
とここで、こんな疑問が湧いてきませんか。
- そもそも「精油」って何?
- 「アロマオイル」とどう違うの?
- 精油ってどんな油を使ってるの?
ということで今回は、そんな「精油のきほんアレコレ」をお伝えしていきます。
- AEAJ(公益社団法人日本アロマ環境協会)アロマセラピスト&インストラクターとして、ワークショップ出店やアロマ講座の講師を経験していたりする。
- ついつい頭で考えすぎてしまいがちな私にとって、「スイートマジョラム」の精油は、「考えるな!感じろ!」に瞬間シフトできる最強のツールである。
あくまでも私個人の考察や体験ですので、参考程度にとどめおいていただけると幸いです。
精油とは、植物が作り出した芳香物質を抽出したもの


「精油」とは、植物が作り出した芳香物質だけを取り出したものです。
精油は、「エッセンシャルオイル」とも表現されますが、どちらも同じ意味になりますので、この記事では、「精油」で統一して表現していきたいと思います。
芳香物質とは、においとして感じられる香りを放つもので、多くの香りの成分が集まってできた有機化合物。



イメージとしては、「香りのもと」のような感じでしょうか。
では、その香りのもと(芳香物質)はどうやって取り出すの?ということですが、それは「水蒸気蒸留法」をはじめとしたさまざまな方法で取り出せることができます。
例えば、こんな感じで。


ただ、今回はそれを話すと長くなってしまいますので、また別の機会に記事にしていければと考えています。
さて、ここで「精油の定義」についてをお伝えしていきますが、私が会員になっている「AEAJ(公益社団法人日本アロマ環境協会)」では、精油のことを次のように定義しています。
AEAJ 精油(エッセンシャルオイル)の定義
精油(エッセンシャルオイル)は、植物の花、葉、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから抽出した天然素材で、有効成分を高濃度に含有した揮発性の芳香物質です。各植物によって特有の香りと機能をもち、アロマテラピーの基本となるものです。
引用元:AEAJ公式サイトより
精油は、植物の花や葉、果皮などから芳香物質のみを抽出しているので、かなり凝縮をされています。
大量の植物を使い、手間も時間もかかるわりには、取れる量はごくわずかなので、たいへん貴重なものといえるのです。



100%植物由来の天然もの、それが精油です。
しかし、一見すると安全に思えるこの精油ですが、高濃度ゆえに香りが強く刺激があるものもありますので、実は必ずしも安全とはいえないのです。
そう、かなり大袈裟にきこえるかもしれませんが、実は精油は「劇薬」だったりするのです。
また、人によっては、特定の植物(精油)に対してアレルギー反応等を起こす場合も少なくありません。
だって、雑草でも食べられるものとそうでないもの(毒)がありますでしょ。きのこなんて最たるものですよね。(少し脇道に逸れた感がありますが、植物つながりということで)
AEAJでは、使用する際には次のような注意を促しています。
精油を安全にご使用いただくための注意事項
①精油原液を皮膚につけない
②精油を飲用したり、うがいに使用したりしない
③火気のそばで使用しない・精油や植物油が付着した試香紙やティッシュは水で湿らせてから処分する
引用元:AEAJ公式サイトより
・精油や植物油がついたタオルなどは乾燥機の使用をさけ、天日干しにする
④精油を目に入れない
⑤子どもやペットの手の届かない場所に保管する
アロマテラピーを楽しむためにも、安全に適切に精油を扱うことは基本中の基本なのですよね。私も常々気をつけていますよ。
アロマオイルと表記されていても、合成香料であれば精油ではない


精油は、「天然である」ということがポイントです。
ということは、人工的に合成された香料(合成香料)は、精油とはいえないということです。
例えば、よく目にしたり耳にする言葉に、「アロマオイル」とか「ポプリオイル」、「フレグランスオイル」なんていうのはありませんか。
実は、このような表記で販売されているものは、もちろんすべてではありませんが、合成香料の可能性が否めません。
そして、もしそうであれば、それは精油ではないということになります。
では、ほんまもんの精油を入手するにはどうすればいいの?ということですが、一例として挙げていきます。
- アロマテラピーの専門店で購入する
- 商品のパッケージやビンに表記されている内容をよく確認する
それ以外にもありますが、これもまた後日、詳しく記事にしていく予定です。
AEAJの公式Webサイトにも、精油の正しい選び方が掲載されていますので、ぜひ参考になさってくださいね。
「合成香料」にもそれなりの利点はありますが、「天然ものが欲しい」ということであれば、入手時に見極めることをお勧めします。
植物が香りを放つのは、自分を守り子孫を残すため
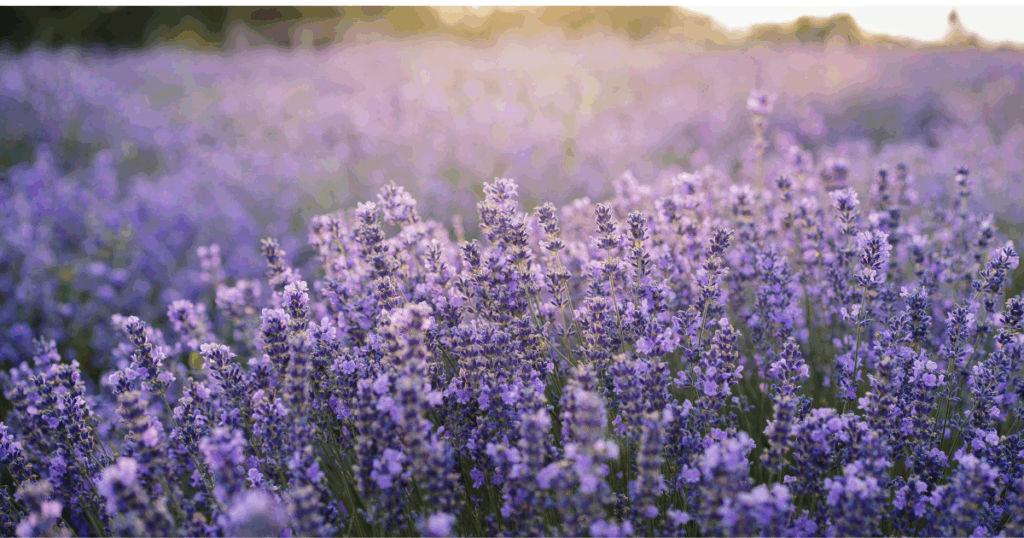
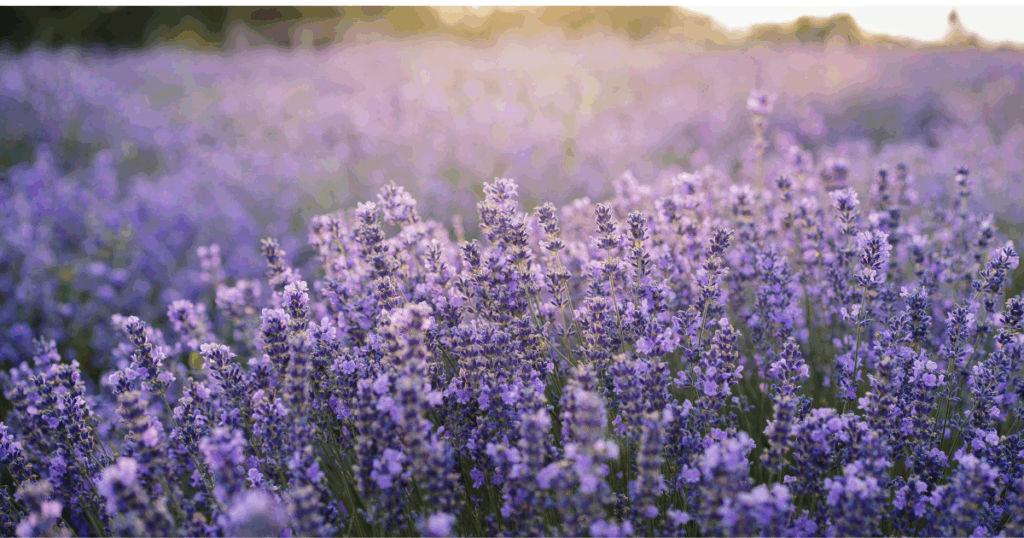
ご存知のとおり、植物は二酸化炭素を取り込み、光合成によって糖質や脂質、タンパク質などの必要な栄養素を自ら作り出します。これを、一次代謝産物といいます。
この一次代謝産物を原料として、さまざまな二次代謝産物が作られますが、精油もこの二次代謝の過程で作られるのです。
精油の他に、ポリフェノールやカテキン、カロチン、カフェインなども、二次代謝産物といわれます。
このように作られた芳香物質である精油ですが、どんな目的で何のために作られるのでしょうか。以下、主なものをまとめてみました。
| 誘引(ゆういん)作用 | 虫や鳥を引き寄せ、受粉したり種子を運んでもらうために、芳香物質を作ってアピールする。 |
| 忌避(きひ)作用 | 虫や鳥などが必要以上に寄ってこないように遠ざけ、葉などが食べられたり傷つけられたりすることを防ぐため。 |
| 抗菌作用 | 自分にとって有害な菌や真菌には、繁殖しないように殺菌、抗菌、抗真菌物質を出して身を守っている。 |
| 冷却作用 | 太陽の熱から身を守るため、蒸発をして自らを冷却させる。 |
| 成長に関する情報伝達物質 | 植物内で、神経伝達物質の役割をする。血液中に流れるとホルモンのような働きをする。 |
| 生理的老廃物説 | 植物内で不要になったものという説もある。 |
これを見るに、植物が香りを放つのは、「自分を守るため」「子孫を残すため」であり、生物としては「あたりまえ」のことをしているだけだったのですね。
植物にとって、生きるためにとても大切である香り。
それを「あたりまえ」とは思わず、植物の恵みに感謝をしながら大切に使わせていただこう・・・アロマを勉強するようになってから、その想いはより一層強くなったように思います。
植物によって、芳香物質を作り出す部分はさまざま
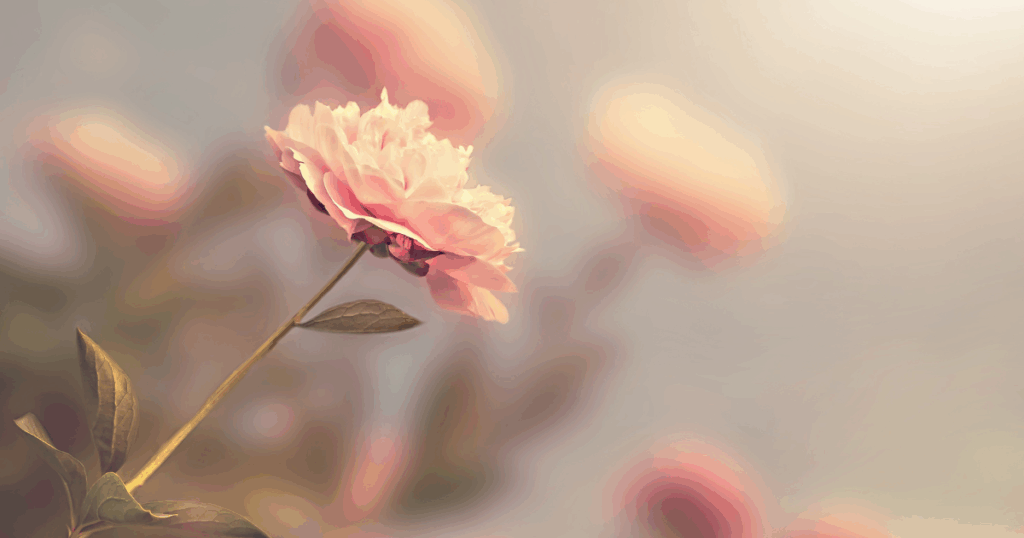
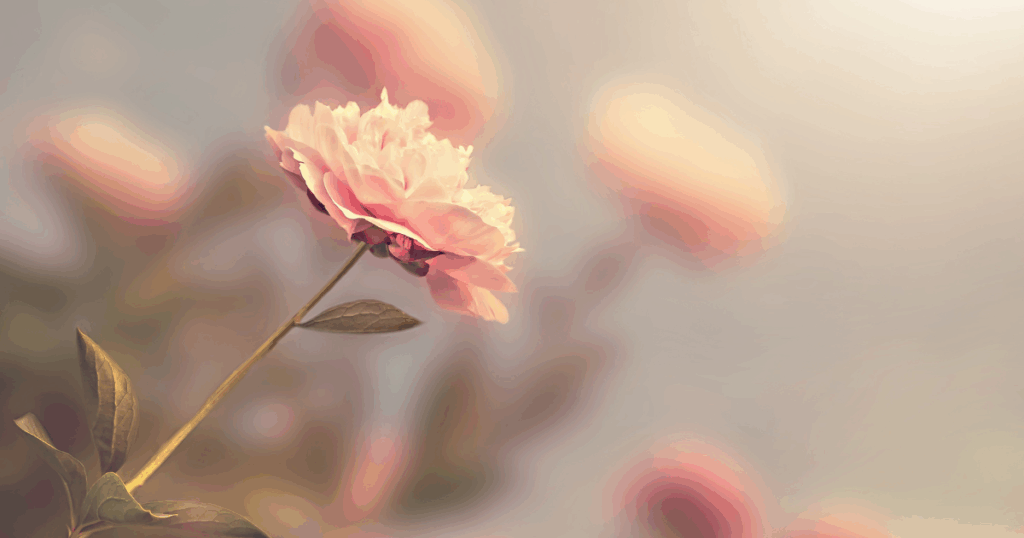
香りのもとである芳香物質が分泌される部分は、植物によってさまざまです。
また、精油がとれる量も異なるため、精油の価格に差が出るのです。
例えば、高価な精油の代表格といえば「ローズオットー」ですが、水蒸気蒸留法で抽出した場合、バラの花数50輪から100輪分で精油1滴分だともいわれています。
バラの花びらにある芳香成分は水に溶けやすいという性質を持つことから、精油の抽出量が少なくなってしまうというのが、理由の一つといえるでしょう。
バラというのは、どこまでも「高嶺の花」なのですね。
以下に、どの精油がどこの部位から抽出されたのかの一例を挙げていきます。
花


- イランイラン
- カモミール・ジャーマン
- カモミール・ローマン
- ジャスミン
- ネロリ
- ローズオットー
- ローズアブソリュート
など
葉


- スイートマージョラム
- ゼラニウム
- ティートリー
- パチュリ
- ペパーミント
- ユーカリ
- レモングラス
- ローズマリー
- メリッサ(レモンバーム)
- タイム
- バジル
- シトロネラ
- ハッカ(薄荷)
- 月桃(ゲットウ)
- ローレル(月桂樹)
など
花と葉


- クラリセージ
- ラベンダー
- ヤロウ
など
葉と果実


- サイプレス
など
果実


- ジュニパーベリー
- ブラックペッパー
など
果皮


- オレンジ・スイート
- グレープフルーツ
- ベルガモット
- レモン
- マンダリン
- ユズ(柚子)
など
木部(心材)


- サンダルウッド(白檀)
- シダーウッド
- ローズウッド
- ヒノキ(檜)
- 青森ヒバ
など
樹脂


- フランキンセンス(乳香)
- ベンゾイン
- ミルラ
など
根


- ベチバー
- ジンジャー
など
種子


- コリアンダー
- フェンネル
- カルダモン
など
今回ご紹介した精油がすべてではありませんが、抽出部位は「葉」が一番多いことがわかります。それだけでも、なんだかアロマテラピーが身近に感じませんか。(そんなふうに感じるのは、私だけかしら?)
ちなみに、精油の種類は、500種を超えるといわれています。
アロマセラピストが使う精油はだいたい50種ほどのようで、私も50種類弱の精油を持っていますが、なかには100種類ほど用意されているセラピストさんもいらっしゃるようですよ。
精油の主な特徴は芳香性・揮発性・親油性であり、油脂ではない


精油にはさまざまな特徴がありますが、代表的なものを挙げていきます。
- 芳香性
- 香りをもっているということ。香りは、各精油の芳香成分の組み合わせによって変わってくる。
- 揮発性
- 常温で空気中に発散され、時間とともに消えていく。
- 親油(しんゆ)性
- 油脂に溶けやすい。油溶(ゆよう)性、脂溶(しよう)性ともいわれる。
それから、よくある疑問に、「精油は油なのか」というものがあります。
こたえとしましては、精油は、油という文字が使われてはいるものの、いわゆる植物油のような「油脂」ではありません。精油とは構造の違う全く別の物質なのです。
・・・なんてことを偉そうに語っているわたくしではありますが、アロマの勉強をするまでは、精油は油の一種かと思っていたことを、ここで白状しますよ(笑)。
まとめ


精油の基本となることをざっくり挙げてみましたが、最後に今回の内容をまとめてみます。
- 精油とは、芳香物質だけを取り出して凝縮したもの。必ずしも安全とはいえないため、取り扱いには注意すること。
- 精油は天然であることがポイント。例えば「アロマオイル」と表記されていたとしても、合成香料であれば精油ではない。
- 植物が芳香物質を作る目的は、誘引作用や忌避作用など自分を守り子孫を残すためのもの。
- 芳香物質を作り出す植物の部分は、葉や花、果皮など植物によってさまざまである。
- 精油の主な特徴としては、芳香性、揮発性、親油性である。そして、精油は油脂ではない。
できるだけ専門用語的なものを使わないように、わかりやすい例えを出してご説明できればよかったのですが、ちょっとお堅い感じになってしまいました。まだまだ未熟なうえ、お許しくださいませ。
それでも、これを機に、少しでも精油を身近に感じていただけたのであれば、とてもうれしいです。
このような長文を、最後までスクロールしてくださり、ありがとうございました。